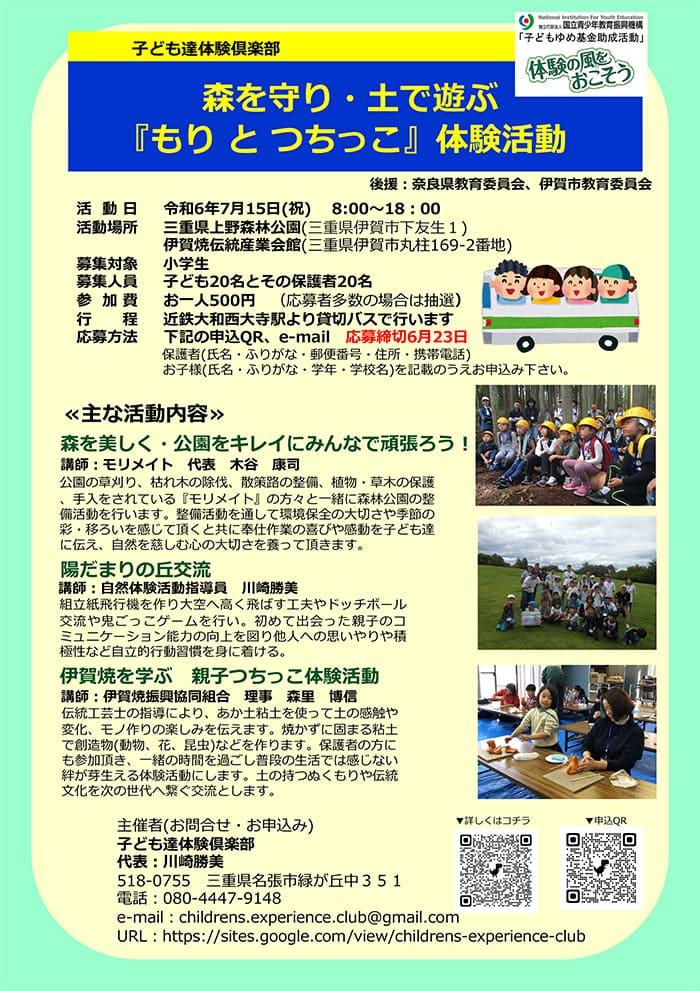2023.2.17
基本情報 Basic Information
史跡 郡山城跡/こおりやまじょうせき
- 住所: 奈良県大和郡山市城内町
- 営業時間: 天守台展望施設/4~9月:7:00~19:00、10~3月:7:00~17:00
- アクセス: 近鉄郡山駅から徒歩約7分、JR郡山駅から徒歩約15分
- 駐車場: あり
-
TEL:
0743-52-2010(大和郡山市観光協会)
※盆梅展に関するお問い合わせは大和郡山市地域振興課(0743-53-1151)