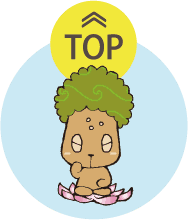《連載》
新日本妖怪紀行|第25回
相撲の祖、野見宿禰の物語
『日本書紀』に相撲の力士、野見宿禰の話があり、天皇の前で初めて天覧相撲を行いました。また、陵墓に埴輪を使うことを進言し、臣下の人たちを生き埋めにする習慣を改めさせた、とも書かれています。
力があり頭も良かった人物で、「のみ」と言っても小さくはなかったんです。えっ「だじゃれはいいから早く始めろ」って。はいはい、では野見宿禰の物語、はじまりはじまり〜。
当麻蹶速 VS 野見宿禰
「大和の当麻に当麻蹶速という、獣の角を折ったり鉄の鉤を引き伸ばしたりする剛力の者がいます」と、垂仁天皇の側近が天皇に告げました。また「世の中に、自分と並ぶような力のある者がいるなら、生死を賭けても、その者と力くらべをしてみたい」とも言っている、と。それを聞いた天皇は、さっそく群臣を集め、「当麻蹶速は天下の力士。これに並ぶ勇士はおらぬか」と、おたずねになりました。すると一人が「出雲国に野見宿禰という勇士がいます。この者と対戦させてみてはどうでしょう」と言い、天皇はさっそく野見宿禰を呼んで、当麻蹶速と相撲をさせるよう命じました。
当時の相撲は、まず蹴り合いから始まります。2人は合図と共に立ち上がると、互いに激しく蹴り合いました。結果、宿禰が蹶速の肋骨を折り、腰を踏みくじいて殺しました。そして宿禰は蹶速の領地を与えられ、大和に留まって天皇に仕えることになったのです。

埴輪は野見宿禰の考案?
もうひとつ、『日本書紀』に宿禰が埴輪を考案した話があります。
当時、天皇や高貴な方が亡くなると、生前仕えた人々を陵墓の周囲に生き埋めにしました。垂仁天皇の皇后、日葉酢媛命が逝去された際、宿禰は、君主の陵墓に生きた人を埋める殉死の風習を改めて、埴輪を埋納するように進言しました。そして、出雲より土師部を呼んで、人や馬に見立てた埴輪を粘土で作って、御陵の周りに埋めたのです。つまり、みなさんご存じの埴輪は、『日本書紀』によると宿禰の考案だったのですね。
国技発祥の地の神社
野見宿禰伝説は各地にありますが、奈良には明治16年まで「野見宿禰塚」がありました。現地の案内板によると、直径20メートルもある豪壮な塚で、その上に巨大な五輪塔がのっていたということです。しかし、なぜか明治16年に突然、取り壊されました。五輪塔は、近くの十二柱神社の境内に移設されたということです。そこに行くと、最初に狛犬が気に入りました。狛犬を支えているのが小さな力士たちで、なんともかわいいのです。
そこから、日本で初めて天皇がごらんになった「天覧相撲」が行われた場所にある「穴師坐兵主神社」の摂社「相撲神社」にも行きました。案内板に、ここは国技(相撲)発祥の地とあり、昭和37年に、当時の日本相撲協会の時津風理事長(元横綱双葉山)、2横綱(大鵬・柏戸)、5大関など、幕内の全力士が参列して大祭が行われた、と記されていました。境内には大きな土俵もあります。

もともと相撲は神様の前で行う儀式的性格が強く、単なるスポーツではありません。そんな相撲の意味を感じながら丘の中腹にある相撲神社から、坂道をゆっくり下っていくと「纒向遺跡」の案内板がありました。ここは前方後円墳が集中していることや、農耕具より土木工事用の工具が圧倒的に多く出土していることから、一般的な集落とは違う都市、つまり邪馬台国があったのではないか、と書かれていました。
そう思うと、眼下に邪馬台国の風景が広がりました。そんな想像の都市を眺めつつ、山辺の道を、力士になった気分でゆっくりと下ったのでした。



*掲載内容は2017年8月に取材したものです