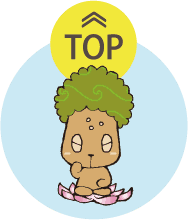現代の〝国民病〟といわれるほど増加傾向にある糖尿病。自覚症状が現れにくく、進行すると合併症を招くなど命にかかわる怖い病気だ。「奈良県糖尿病診療ネットワーク専門協議会」の一員としてケアチーム一丸となって患者のサポートに当たっている西の京病院糖尿病内科で、専門医の石塚健・藤村真輝両医師に新規作用機序の薬も含めて話を伺った。

糖尿病内科医長
藤村 真輝 医師/FUJIMURA MASAKI
(写真左)
先生の健康法
昼食の炭水化物を減らし、週1でスポーツジム。病院では階段を使います。
糖尿病内科部長
石塚 健 医師/ISHIZUKA KEN
(写真右)
先生の健康法
電車通勤の前後、往復80分を徒歩で。さらに他科に入院中の患者さんの血糖管理のため院内各棟を歩き回っています。
- その症状、糖尿病かも。要注意デス!
糖尿病は、インスリン(すい臓から分泌されるホルモン)の分泌量やその作用が低下し、血液中のブドウ糖が増えてしまう病気。これを高血糖といい、この状態の慢性的なものが糖尿病だ。
口喝
多飲
多尿
体重減少
のような症状があったら要注意!すぐに専門医を受診しよう。
- 95%以上が2型糖尿病。その原因は!
糖尿病患者の95%以上を占めるのが2型糖尿病。40代以上に多いが、若年発症も増加中だ。遺伝的なものもあるが、食べ過ぎ・運動不足などの生活習慣の乱れが原因で発症する。
- 血糖値126mg/dl・HbA1c 6.5% 以上は糖尿病
採血検査(1〜2か月の平均的な血糖値検査)で、空腹時の血糖値が126mg/dl以上、(正常値110g/dl未満)HbA1c(へモグロビン数値)6.5%以上(正常値6.0未満/糖尿病型)は、糖尿病と診断される。それら未満の数値を境界型と呼び、糖尿病予備軍なので生活習慣を見直すことが大切だ。
-
怖いのは合併症とがんリスク
合併症の有無・程度の総合検査を
初期の糖尿病は自覚症状が現れにくく、神経障害、網膜症、腎症や心筋梗塞など、知らないうちに忍び寄
る合併症が怖い。「また糖尿病があると、すい臓、肝臓、大腸のがんリスクが高まります。定期健診を怠らないことです」と先生。
▲
合併症予防のための目標は
HbA1c 7.0%未満
HbA1c 7.0%未満
- 治療の基本は食事療法、運動療法。その次に薬物療法
「血糖コントロールの基本は、食事と運動です。生活習慣を見直し、必要な量をバランスよく食べることと、無理なく楽しめる運動(食後がベター)の継続がカギです」と先生。
食事療法
- 適正なエネルギー量
- 栄養バランス
- 規則的な食事習慣
▲
寝る前に甘いもの(果物も)
を食べない。
を食べない。

運動療法
筋肉は糖の消費だけでなく、糖の貯蔵庫として働くので、運動を習慣化して、糖を取り込みやすく、インスリンの効きがよくなる体を作る。
薬物療法・・・肥満治療にも!
食事や運動療法を頑張っても血糖コントロールができない場合には、飲み薬やインスリンなどの注射薬で治療する。
なかでも、食欲抑制作用がある新しい作用機序(仕組み)の薬(GLP-1受容体作動薬)を使う頻度が高くなっており、「これは、肥満症治療にも使うようになってきています」とのこと。肥満症に悩む方は相談してみよう。
注・肥満症…単なる肥満ではなく、健康障害を合併した肥満

- 教育入院や糖尿病教室実施中!
同院では「教育入院」(原則2週間)で、糖尿病治療の生活習慣を身に着けるサポートのほか、「糖尿病教室」を隔月開催中。
糖尿病教室
\ 申し込み不要・参加費無料 /
会 場
メビウスホール(4階)
日 時
8月19日(火) 14:00~15:00
テーマ
「運動でフレイルを予防しよう」
講師:理学療法士
講師:理学療法士
「フットケアの実際」 講師:看護師

\
専門医を中心に糖尿病ケアチームが
治療をサポート!
/
糖尿病ケアチーム(医師・看護師・栄養管理士・薬剤師・理学療法士・臨床検査技師・放射線技師など多職種)が連携を取り、糖尿病合併症の有無や程度を調べる詳細な診察・検査・指導を行い、治療方針の見直し等に取り組んでいる。

つらい自己管理も楽しく
続けられるようお手伝いします♪
続けられるようお手伝いします♪
■問い合わせ/患者支援センター TEL.0742-35-2219
■取材協力/医療法人康仁会 西の京病院 奈良市六条町102-1/
https://www.nishinokyo.or.jp/