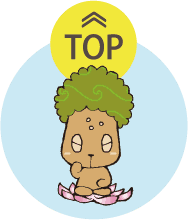《連載》
新日本妖怪紀行|第29回
弘法水の不思議
「薬井」と「大師の硯石」
弘法大師(空海)には「ほんまか?」と言いたくなるような伝説が数多くあります。
例えば、年老いた夫婦が弘法大師に宿を提供して、そのお礼にもらった手拭いで顔を洗うと若返り、他人に貸したらその人は猿になったとか、とんでもない話がいろいろあります。今回はその中でも、弘法大師が地面を杖でコツコツたたくと泉が湧いた、などと言われる弘法水の話をお届けします。

弘法水で眼病が治った!
まず、北葛城郡河合町薬井へと向かいました。近鉄「大輪田」駅から少し歩いて、車が1台通れるぐらいの道をくねくね行くと、目指す井戸がありました。言い伝えによると、この地に弘法大師(空海)が訪れたとき、眼病を患っている人を気の毒に思い「ここを掘ると水が湧く、それで目を洗うがよい」と、教えてくれました。その人が目を湧き出した水で洗うと、たちまちのうちに眼病が治り、近隣の村々からも水を汲みに人がやってきたというのです。
現地にあった案内板にも「近年までは美しい水があふれ出していて、村人も飲み水として使用していた」と、書いてありました。このように、薬になる水を湧かせた伝説は全国にありますが、ここの「薬井」は地名にもなっていて「薬井水」と刻んだ古い石も、傍らにありました。
弘法水は全国1400か所以上!
弘法大師は、このように薬になる水を湧かせたり、飲み水の不足している地域では井戸の場所を教えたりしました。弘法井戸、弘法清水、弘法水などと呼ばれる湧き水は全国にあって、その数も1400以上という調査結果もあります。分布はやはり高野山のある近畿地方から、八十八ヶ所霊場のある四国に多いのですが、青森から鹿児島まで存在します。
小麦粉でも、先生から「酔い止めの薬です」と言って渡されたら、誰もバス旅行で酔う生徒がいなかったということを聞いたことがあります。まして当時、絶大な法力の持ち主、弘法大師の水と思えば、病気によっては本当に治ってしまう人もいたことでしょう。
でもこれらは、弘法大師がすごいと言うより、普通の人がただの水を薬の水だと体に思い込ませる、または水自体を薬に変える力があると考えた方がいいでしょうね。今の我々は、弘法大師を信じる前に科学的分析を信じる傾向にありますから、水を薬に変えることはなかなか難しそうです。

山と海が通じる岩?
もうひとつの伝説は「大師の硯石」と呼ばれるもので、山辺郡山添村大塩にあります。それは幅4㍍、長さ3㍍の大岩で、岩の上に深さ20㌢ほどのくぼみがあり、いつも水がたまっていて、枯れることがないというものです。
昔、弘法大師が村人に「困っていることはないか」とたずねると「塩がないので暮らしがたいへんです」と答えました。「それならここに山塩が出るようにしてやろう」と言い、持っていた錫杖で岩をたたくと、穴がポカリと開き、そこから海の潮が湧きました。大師はその潮から塩を取って村人に与え、それからこの地域を「大塩」と呼ぶようになったということです。現地ではたしかに大岩のくぼみに水がたまっていました。海がこの岩に通じているということなのでしょう。
でも実は私、ひとつ残念なことをしました。せっかく山の上まで来たのに、岩にたまった水が本当に塩からいのか、確かめもせずに下山したことです。ああ、一生の不覚。ひとなめすればよかったのに……。



*掲載内容は2017年12月に取材したものです