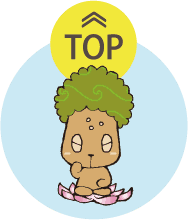《連載》
新日本妖怪紀行|第26回
道路に鎮座する神様仏様
道路の真ん中に大きな木や神社、地蔵などがあって、車が避けて通らなければならない所が、日本全国あちこちにあります。どうしてそんな危険な所にわざわざ祀ってあるのか、不思議に思う人も多いことでしょう。
今回は奈良市の道路の中から、道に鎮座する神様や仏様をピックアップしてみました。
地蔵と弘法大師の井戸
まず最初は二条町交差点の2つの地蔵堂。1つは大きな地蔵と小さな地蔵がお堂の中に並んでいて、もう1つのお堂には弘法大師の井戸と地蔵が3体ありました。井戸をのぞいてみましたが、深すぎて底がどうなっているのかわかりません。弘法大師が水の出る場所を村人に教えて、掘ってみると水が湧いた、という伝説は日本中にあります。きっとそのようないわれの井戸なのでしょう。

とにかく2つのお堂が交差点のど真ん中でかなりの面積を占めていて、車はビュンビュンその横を走っています。地元の人に聞くと、昔はそこにお寺があってその門の前にあった地蔵らしく、区画整備などで寺は移転し、地蔵だけが残ったということです。でも「わしらの生まれる前の話だかんね〜」ということで、詳しいことはよくわかりません。
実は北向き? 歌姫街道地蔵堂
次の目的地は隣の佐紀町の地蔵堂なのですが、それらしい場所が見つかりません。うろうろしていると駐在所があって「どこ行くの?」って、巡査さんが声をかけてくださいました。わけを話すと地図まで書いて教えてくれたのです。
さっそく行ってみたら、ちょうどその日は地蔵盆で、地元の人が準備をされていました。お聞きすると、ここは昔、工場の敷地で工場のそばにあった地蔵だそうです。いつしか工場はなくなり、地蔵堂だけが残りました。また、地蔵が今は南を向いていますが、元は北向きの地蔵だったということです。地図上では歌姫街道地蔵堂とあり、きっとこの付近に、平城宮で雅楽に合わせて舞った女官たちが住んでいたのでしょう。
3つ目は同じ佐紀町ですが、そばに池があり、2つの道が交わる所にありました(ここも巡査さんに教えてもらいました)。立派な木の下に地蔵がきちんと配置されていて、ちょっと休憩するのに気分の良いところです。

道路の中から動かせない理由
さて次は、JR奈良駅からひと駅、京終駅で降りてすぐのところの椚神社です。クヌギの霊木を中心に囲いがあり、道路の半分を占拠しています。一説によると弘法大師がクヌギでできた杖を地面に刺したら、それが根付いて木になったと言われています。しかし弘法大師って、ホント神出鬼没。全国どこにでも現れ、伝説になってますね〜。
他の地域でもよく言われるのが、道をふさぐ霊木が邪魔だから切ろうとすると、作業員が亡くなったとか、木から血が出たとか、たたりが怖くて残しているという、まことしやかに語られる都会の怪談。でも実際は、霊木も地蔵も土地を守っているので、おいそれと移動できないというのが本来の理由です。移転されてしまっては、その土地を守ることができなくなるのです。作り話の怪談に、彼等の存在理由など見つかりません。
また、取材日は奈良のあちこちで地蔵盆があったようです。地元の人が地元を愛し、地元で生きることの象徴である霊木、地蔵や神社。それらを昔のままにその場所で守り、保存することの意義は、道路のど真ん中とはいえ、確かにあるのです。
楽しく語らいながら地蔵盆の準備をする人々の姿を見て、そんなことを改めて考え直した一日でした。




*掲載内容は2017年9月に取材したものです